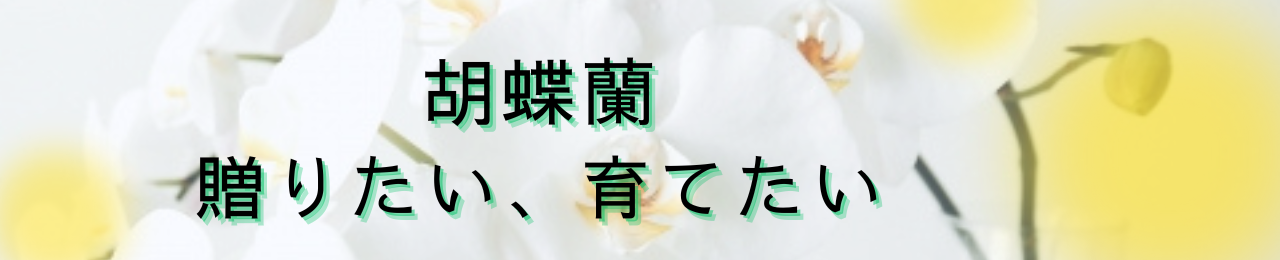ビジネスシーンにおいてもプライベートシーンにおいても、
花束を贈ることはあっても「胡蝶蘭を贈った経験がない」という方は多いですよね。
胡蝶蘭を贈る際に気をつけたいマナーのひとつに「立て札」があります。
立て札は、贈り物につける熨斗(のし)のような存在になります。
立て札について
「立て札」を付ける理由には、
・贈られた側と贈り主との関係を対外的にアピールする
胡蝶蘭に立て札を付けることの意義はとても大きいのです。
だからこそ、胡蝶蘭を贈る際の立て札のマナーについて、知っておくことが重要ですね。
立て札の見本

お祝い事の見本になりますが、朱文字でお祝いの言葉を記し、贈り主の名前を入れるのが一般的です。
宛名は入れても入れなくてもよいのですが、贈るお相手との関係などを考慮して、必要であれば入れましょう。
贈り主や宛名が英文字など横書きの方がしっくりくる場合もあるでしょうから、横書きを希望する場合はショップに伝えると
バランスよく横書きタイプを用意してもらえますよ。
「立て札の種類」は主に
・紙材に木目をプリントしたもの
・厚みのある木材にさらに美しい木目をプリントしたもの
・白またはデザインが入った紙材
があります。用途に合わせて使い分けを見ていきましょう。
ビジネスシーン
ビジネスシーンであれば、白地の紙材よりも木目調の立て札が向いています。
また、特別なお相手ならば厚みのある木製の木札をおすすめします。
木目調の紙札よりも、厚みのある木製は重厚感が増し、特別感がでます。
プライベートシーン
プライベートシーンでは誕生日や長寿のお祝いなど、特に贈り主を対外的にアピールするまでもない場合が多いですね。
白地やデザインのある紙素材でも失礼ではありません。
また、メッセージカードもおすすめです。
メッセージカードであれば、立て札よりもたくさんのメッセージを記入できるので、
お祝いの気持ちや感謝の気持ちをしっかり伝えることができますよ。
立て札の書き方
贈るお相手に失礼のないよう、ショップへ贈る目的をきちんと伝えておきましょう。
ただし、用途を迷う場合は「御祝」としておくと無難です。
開院、開業、開店、移転
頭書きにあたる朱文字は
「祝御開院」「開業御祝」など、前か後ろにお祝いの文字を入れましょう。
届ける日は、当日よりも前日が一般的ですが、先方の都合を事前に確認しておくことをおすすめします。
一般的には白い胡蝶蘭を贈るのが無難ですが、コーポレートカラーのあるお相手であれば、合わせた花色の胡蝶蘭でも喜ばれるでしょう。
また、商売繁盛を祈念するお祝いであれば「黄色い胡蝶蘭」も金運をイメージするため喜ばれます。
就任
頭書きにあたる朱文字は
「就任御祝」「社長就任御祝」
届ける日は、前任者との交代が済んた後、就任した日がよいです。
早めに届いてしまうと前任者の方に失礼となります。
就任式があるならば、式当日の朝がよいでしょう。
周年祝い
頭書きにあたる朱文字は
「祝 ○○周年」
「祝 設立○周年」
届ける日は、記念式典の当日の朝が理想ですが、先方の都合を聞いて贈る日時を決めると親切です。
新築祝い
新築祝いは個人的な贈り物であることが多く、特に立て札は必要ない場合が多いです。
立て札を付ける場合でも、「新築御祝」「祝御新築」とし、対外的にアピールする場合は贈り主のお名前を入れると良いでしょう。
その他お祝い事
上場祝い、当選祝いなど、胡蝶蘭を贈るシーンは他にもありますが、立て札に迷ったときは購入するお花屋さんにアドバイスをもらうと間違いないでしょう。
御供

基本的には白い札を使います。
お祝い札であれば、宛名を入れることもありますが、御供の立て札には宛名(故人や個人のお身内のお名前)は入れません。
贈り主のみを書き入れます。
複数人の場合は「○○有志」「○○一同」とすることが一般的です。
まとめ
胡蝶蘭を贈る場合、立て札を付けるというマナーがあります。
ただし、すべてに必要なわけではありません。
立て札が必要なシーンは、特にビジネスシーンにおいての場合が多いです。
お祝いとお悔みのどちらにも立て札を付けますが、用途によって材質や文言が変わりますので注意して、失礼のないようにしたいものです。